資源循環の鍵はトレーサビリティ? -サーキュラーデザインにおけるDX活用を考える-
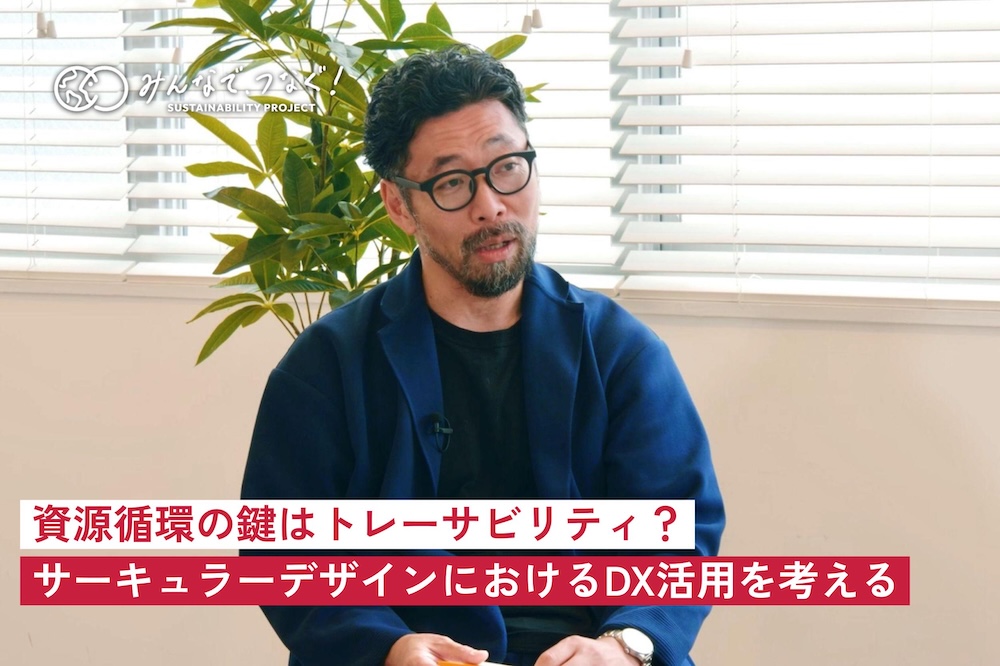
サーキュラーデザインを語る座談会・前編 では資源回収をどうデザインするか、ECOMMITと当社の連携を中心にお伝えしました。中編はサーキュラーデザインのこれまでの流れや国内外の動向、サステナビリティをどう実現するか、についてお届けします!
デザインの力でサステナビリティを実現するには?
世界一の美大と言われる、ロンドンの「ロイヤル・カレッジ・オブ・アート」(以下、RCA)で修士号・博士号を取得され、その後学んできた内容を日本で教えたり、研究したりしてきたという水野大二郎さん。そんな水野さんですが今までのデザイン人生について「反省中」だと言います。一体どういうことなのでしょうか?
水野:RCAで学んでいた時は2000年代で、とにかく審美性重視のデザインをする時代で、帰国後も審美性にまつわる独創性をどう高めるか、これをベースにデザインを教えていました。しかし2015年頃から製品やサービスの開発において、デザイン業界がこれまで良しとしてきた価値観から、これからの社会や環境の中での「持続可能性(サステナビリティ)」を重要視するものへ変化していきました。これは環境問題の悪化や大量生産モデルへの限界が背景にあります。20世紀でやってきたサーキュラーではないデザインを反省した上で、現在はジャンルを問わず一連の製品開発やサービス開発に携わるようになりました。

大畑:「反省」した結果、水野さんは今、具体的にどのような活動をされているのですか?
水野:モノやサービスよりも大きな「事業戦略」のデザインです。まず必要以上に作らないのが大前提なのですが、それを言うと作って売ってなんぼの世界にいる製造業が大体しかめっつらになってしまいます。そこで最初に考えなければならないポイントは、サービス産業とどう連携させるか。部品・素材の話から製品・サービスそして事業戦略を地続きで行ったり来たりしながら、事業や産業全体のデザインに一番力を入れて活動しています。
資源循環を加速させる「トレーサビリティ」について考える
水野:2015年にSDGsが採択され、ちょうど同じ時期にサーキュラーエコノミーの概念が出始めたので、当時から10年経ちました。気候変動に強靭な発展や開発のあり方など、環境問題に対応する活動のアップデートの震源地は大体EUです。EUは環境問題に端を発して新しい経済モデルを生み出し、そのための新しい条例や制約、標準を作ることでEU自身が生き残ることができると考えている部分もあるのではないでしょうか。
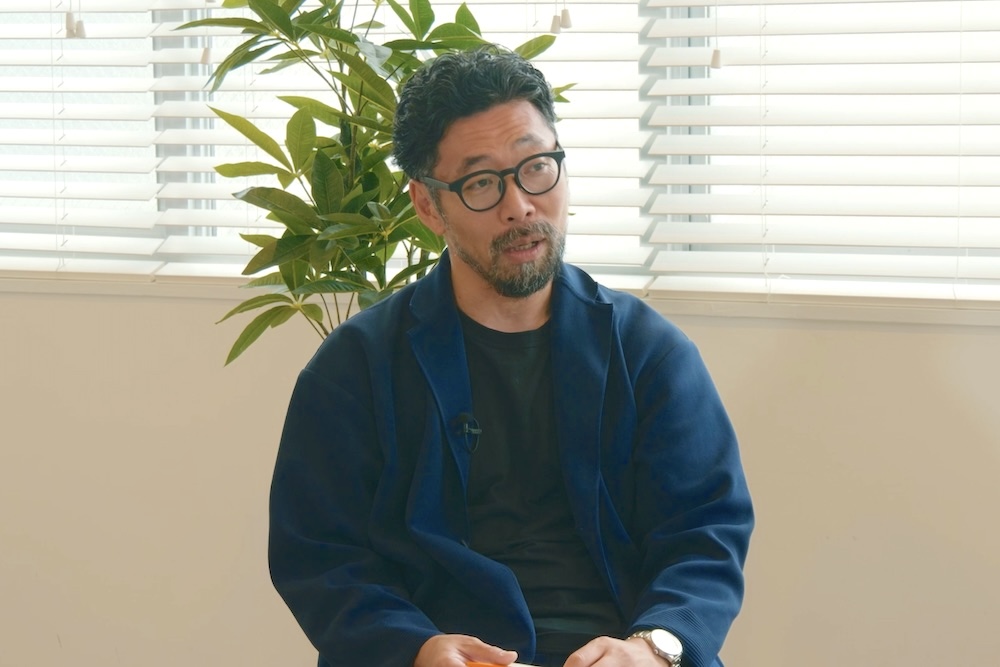
その最たる例が「トレーサビリティ」です。物がどこで作られ、どこを流れて、どこで販売されるのかを全部見える化してしまおうという取り決めです。どのように可視化するかというと、デジタルプロダクトパスポート(DPP)やマテリアルパスポートと言うものを色々な材料や製品にくっつけることで全部データ化してしまうのです。
大畑:具体的にどんな情報がパスポートに記載されるのですか?
水野:どのような情報を記載するか、どのような形で材料や製品にいつからくっつけるかは議論している最中で、日本でも経済産業省を中心にISOやJIS規格のアップデートを議論しています。
こういった標準作りで難しいのが、収益性と環境対応のバランスです。「リサイクル製品」を規定しようとした時にリサイクル繊維の定義(リサイクル繊維が何%入っていたらリサイクル製品と名乗れるのか)を設定しないといけないのですが、今は10%と規定されています。
綿とポリエステルなどを混紡した繊維は機能面でのメリットも多く売れるので、短期的な収益性を重視するなら混紡を選択してしまいますが、混紡された素材は単一素材に比べて再利用・再資源化が非常に困難なんです。現状の産業モデルや収益性の維持を優先すべきか、抜本的に変えないと将来的にまずいぞという危機感が、今せめぎ合っている状態です。中長期的に見たらリサイクル素材比率10%では生き残れません。

デジタルやデザインの力で、資源循環を効率的に実現する
大畑:衣食住の衣類だけでなく食品や建築分野など、業界別の違いや連携の可能性はあるんでしょうか?
水野:たとえば建築だと「BIM(Building Information Modeling)」という建築設計の統合ソフトウェアがあります。建物をつくる際に、建築家の基本設計図面や施工業者の施工図面などさまざまな図面が存在するのですが、それを統合したのがBIMです。BIMでできることは、先ほどお話ししたトレーサビリティを担保するのとほとんど一緒なので、そういう意味で、サーキュラーデザインを取り入れやすい産業として建築業界が挙げられます。
建設時から建材再利用を見込んで、解体しやすくする建築方法がヨーロッパにありますが、日本は地震の多い国なので、同じような方法を採用すると材料自体が劣化したり摩耗したりするのもありますし、そもそも溶接しないと強くならない、みたいなジレンマもあります。循環させる業者と新品を作る業者の両者が、どういう材質でどういう設計だと循環しやすいのかきちんと連携していかないといけませんね。
総じて言えるのは、各産業の特性や国、地域に応じてDX(デジタルトランスフォーメーション)をどう活用するかがポイントになります。
大畑:ここまでのお話を踏まえて、サーキュラーをより進めていくためにECOMMITとしてはどうしていくべきだと考えますか?
山川:私たちの持っているデータをもとに企業と一緒に議論しながら「循環されやすい服」「何回もリユースして何回も色々な人が買える服」を一緒に作っていけたら、資源循環が浸透していく一助になると考えています。
大畑:社会のエコシステムを考えたモノづくりは、サーキュラーデザインの根幹ですよね。

中編ではサーキュラーデザインのこれまでの流れや国内外の動向についてお届けしました。後編は日本のポテンシャルや当社への期待についてお届けします!
>>後編はこちら
